のんびり母さん、小学生から社会人まで勉強時間がどのように変わっているか調べてみた
中学受験に向けて毎日勉強に励む息子キミタロウ。
40代のわたくし、のんびり母さんは高校受験、大学受験のときは、
まあまあ他の学年のときよりは勉強したかな、と思いますが、
子どもの学習時間って全体的に変わってきているのかしら、
そして大学生、大人って勉強してるのかしら、とちょっと調べてみました。
こちらは2018年の記事ですが、ベネッセ総合研究所の研究員の方がレポートしたものです。

こちらの記事によると、1990年から2015年にかけて、
ゆとり教育の影響で、小・中・高校生の勉強時間は1990年から2001年にかけては全体的に減るが、
以降2015年にかけて脱ゆとり教育により学習時間が増えていった、ということでした。
学力が高いか低いか、ということが学習時間に影響していますが、(そもそも学習時間の影響で学力が高いか低いかとも言えますが)
2015年時点で1日の学習時間の小学生の平均時間は96分、中学生は90分、高校生は85分ということでした。
これは塾で学習する時間を含んでいます。
その中で興味深かったのが、子供らに課される宿題量の増加が、
自宅での学習時間の増加につながっている、ということでした。
学校・塾の先生方が子供へ構ってくれる比率が大きくなった、と書かれています。
しかし大学入学後の1日の学習時間に関しては、2015年時点で40分強。
これは昨今あまり変わらない状況です。
また別のサイトでみると、社会人の1日の学習時間は平均6分!
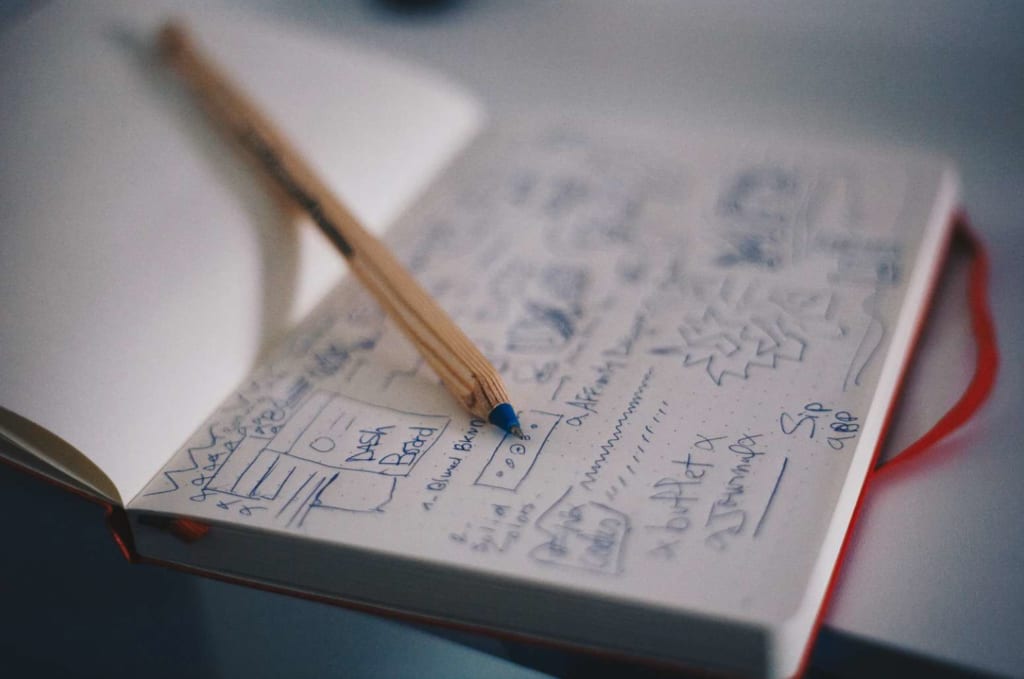
(平均6分といっても高収入、低収入の人で学習時間に差があります❫
たしかになあ、と思いました。
大学の先生は研究活動が主になるから、学部生に宿題なんか出して面倒みる先生はそうそういませんよねー。
海外は違うみたいですが。
学習することが人生の目的ではありませんが、
大人になっても未知のことはいくらでもあります。
それが、大きくなったら知的活動が減る、新しいことを学ぶのをやめる、というのは
非常に残念だなあと感じます。
大人が学習するときは自分が困っていることを解決したい、というのがきっかけになりやすい
あとのんびり母さんが大人になって思ったのは、
大人になってから何かを習得するときのモチベーションとして一番大きいのは
自分の問題解決につながる!ということです。
のんびり母さんはこどもの発達障害について何も知らなかったけれど、
我が子が診断を受けてから、発達障害に関する本を100冊ぐらいは読みました。
そしてできることから実践していったことが、発達障害に関してより関心を深められたことにつながったかな、と感じています。
学習意欲を子供が持つには何が必要か
以上から、学習で大事なことは
学習習慣を身に付けることも大事だけれど、
自分から「これなんだろう?」「あんな大人に自分もなりたい」「稼げるようになるにはどうすればよいのか」「家族で幸せに暮らすには今何ができるのか」などの自分が興味をもって問題を解決したい、という気持ちを大事にすることも大事、ということです。
疑問点を持って調べたり解決したりできる人間に育っていくには、
こどもの頃に自分が大切にされているなあという感覚をもつ、すなわち自己肯定感を持つことがすごく大事だと思います。
わたしが今こども達にできることはなんだろう。
我が家では今朝もこどもにこちょこちょして、ほっぺずりずりして、笑いあってから共に学校へ、会社へ出かけました( ´ー`)



コメント