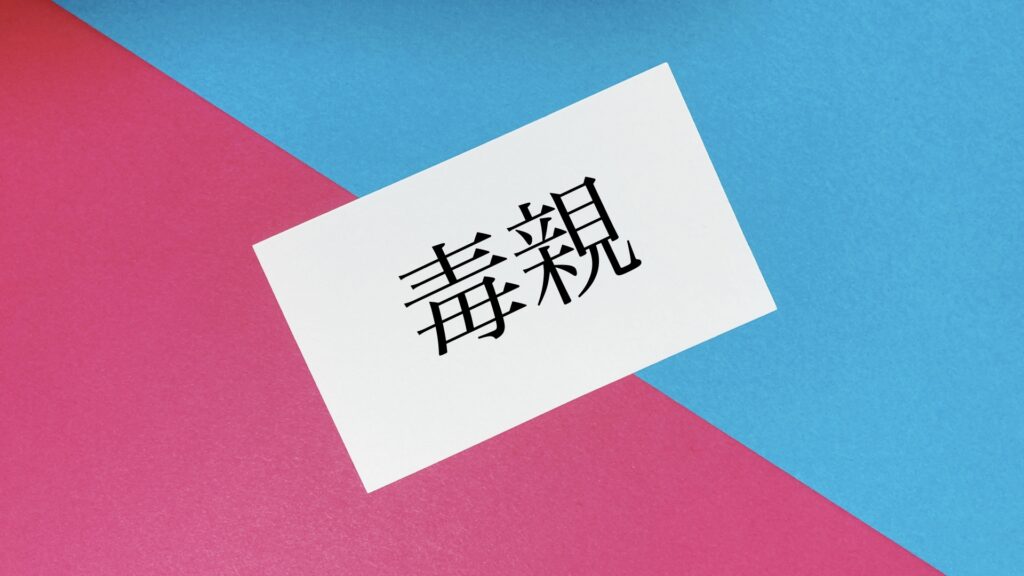のんびり母さんです。
最近、「毒親」という言葉をネットやニュースで見聞きする機会が増えたな、と感じます。
一所懸命子どもの世話をやっているのに「毒」呼ばわりされたら嫌になるわねー、と感じます(苦笑)
毒親の特徴とは
・身体的や言葉による暴力行為をする。
・感情的に不安定。
・食事など世話をしない。無視する。
・子どもの感情を無視して、彼らの自主性を奪うほどの干渉をする。
というものだそうです。
ニュースに出るような事件のような親とは自分は全然違うわ!と以前は思っていましたが、自分も含めて一所懸命に「親業」をやっている人でも注意しないと毒親になる可能性はあるな、と思っています。
発達障害もしくはグレーゾーンのお子さんがいる親御さんは、お子さんの苦手な部分の世話をするとき、苛立つこともあるかもしれません。
またこどもの受験に関わると、こどもがやる気を出さない等で親がイライラすることもあるかもしれません。
自分が毒親にならないために何に気を付けたらいいのでしょう。
今回は自閉スペクトラム症の長男、ADHDグレーゾーンの長女を育てるのんびり母さんが普段気を付けている予防策を3つ挙げます。
子どもの話に耳を傾ける
働きながら子供の世話をする。
ほんと忙しいものです。
専業主婦の人だって、家ではなんやかんやとやることがたくさんあります。
子どもには、年齢相応のことぐらい自分でできるようになっていてほしいし、できていないならあれやこれやと指図してしまいがちです。
でも、そんなときほど、私は「ちょっと待て、なんか子どもは私に言いたいことを言ってきてなかったっけ?」と思いとどまるようにしています。
私が興味のない趣味にハマっている子どもの話を右から左に聞いていなかったっけ?
人は自分の話を聞いてくれる人に好意をもつものです。
そして、好意のある人に、自分がなにか困ったことがあれば相談したいと思うものです。
親にとって大事なのは、子どもが本当に困ってるときに相談に来られるような関係が日頃できているか、だと思います。
子どもにもお母さんには好意を持ち続けてもらってほしいものです。
子どもへかける負荷は子どもの様子を見ながら柔軟に対応する
中学受験を子どもにさせてみて思ったことは、中学受験はかなり子どもに負荷をかける機会となる、ということです。
また、発達障害の子どもを育てた経験から思ったことは、子どもが苦手なことをできるようにするには、負荷が必要、ということです。
負荷がかかる経験がなければ、子どもは自立できません。
しかし、負荷は「適切な質と量」が必要です。
もし子どもがひどい癇癪を起こしたり、心身に異常をきたすようであれば、周囲が、主に親が、方法を変えたり、学校と相談したりなど、本人がもう少し楽に負荷をこなせるように環境を整えてあげればいいのです。
子どもが毎日の生活を充実して送れているか、コミュニケーションを通じてチェックする必要があります。
きょうだいを平等に扱う
「お兄ちゃんだから」「お姉ちゃんだから」「勉強ができるから」「運動ができるから」
きょうだいの中である子をひいきして扱うのは、子どもは敏感に感じ取ります。
私はできるかぎり、小学生のキミコが私と一緒に炊事をしたがるときは、やってもらいます。
中学生のキミタロウが、お母さんの手作りハンバーグが食べたい、と注文をしてきたら作ってあげます。
小さいことなのですが、本人が望んできたことをやってあげれば満足するので、とりあえず今はそんな感じでいいかなー、と思っています。
ご参考になれば幸いです。