幼少期に発達障害の一つ、自閉スペクトラム症の診断を受けたキミタロウの母、のんびり母さんです。
今回は発達障害もしくはグレーゾーンのお子さんを抱える親は、まず本で正しい情報を得ることが大事!という話を書きたいと思います。
キミタロウは現在、普通の、もしくは普通に見える中学生です。
(会話をしているとKYぶりが段々ばれると思いますが(苦笑))
彼は学業では、親の期待を超えるほどのパフォーマンスを見せ、この春は難関校といわれる学校に進学しました。
振り返ると、初めて発達の専門機関で診察を受けた3歳のときは、医師の診察の時間、じっと座っていられないような多動の状態でした。
私は𠮟っていいのか、なだめればいいのか、何をキミタロウにしてやればいいのかわからない、という感じでした。
その後1年通った療育機関で先生方に、どのような点を問題視すればよくて、子どもへどのように対応すればよいのか、色々と教えていただいたことは非常にありがたかったです。
ただ、周囲をみていると、「療育機関に通わせているのに子どもの不適応問題が一向によくならない。」と嘆いているお母さんの話をちらっと聞くと、家庭での対応に一貫性がないことが原因ではないかな、と思えることがありました。
やはり、療育機関に子どもへの対応を任せきりにするのではなく、家庭が中心となって子どもに適切な対応をすることが大事だと感じています。
「子育て本について真面目に読むより、外に出ていろんな体験をさせた方がいい。」という話を聞いたことがあります。
でも私は子どもが発達障害の診断を受け、社会不適応になる可能性があるなら、まずそれを防ぐには親は何ができるのか、情報を仕入れる必要があると思いました。
ブログを書いている私が言うのもなんですが、ブログや動画だと情報の確かさがあやふやな面があります。
本だとブログよりはいい加減なことが書けないので、まずは本を手に取ってみてはいかがでしょうか。
私が読んで参考になった本を一部紹介します。
発達障害の子どもを伸ばす 魔法の言葉かけ

この本は自閉スペクトラム症の男の子をもつお母さんのshizuさんが書いた本です。
私はまず「魔法」という言葉に惹かれて買いました(笑)
キミタロウと同じ自閉スペクトラム症のお子さんを育てる、という面で同じであり、普段お母さんがどのように子どもに声かけをするのかがいかに大事かがよく分かった本でした。
また、週に3つ子どもへの課題を書いて冷蔵庫などよく家の中で目にする場所に貼っておき、それらの課題に取り組んだら、「がんばりましたノート」に記録する、というのは、我が家でも実行しましたが、親子で前進できている感覚が持ててよかったです。
過去にもその様子を書いた記事があります。(過去記事はこちら)
それから、学校でお子さんがいじめにあったとき、shizuさんがどのように対応されたのかが書いてありますが、私も大変参考になりました。
本の最後に書いてある参考図書は、全部読みました。
どの本も発達障害について知識のなかった私には参考になるものばかりでした。
メリットの法則
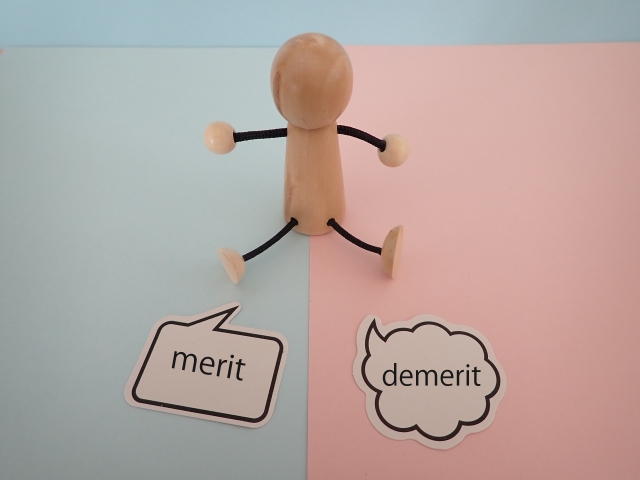
この本は奥田健次さんというカウンセラーの方が書いた本です。
奥田さんは不登校の子供を持つ親御さん達や学校・保育に関わる先生達の間では、「子育てブラックジャック」という愛称がつくほどの方で、多くの子どもたちの問題行動を改善に導いた方なのだそうです。
この本を読んで実践すると、今まで保育の仕事をしていなかった私でも、我が子の問題行動に大体において適切に対応できるようになった、と実感できるようになりました。(その様子の記事はこちら)
子どもへのまなざし

この本は故・佐々木正美さんの著書です。
誰にでも規律などを重んじる「父性」と、受容する「母性」があると思いますが、子どもにはまず「母性」を十分感じる環境を作ってやりたい、と佐々木さんの著書を読んで強く思いました。(過去記事はこちら)
佐々木正美さんが亡くなった後も、時々ブログをのぞいてお世話になっております。
自閉症を克服する

この本は、アメリカで自閉症を克服した親子の記録です。
私はこの本を読んで、幼稚園でキミタロウが同年代の子どもと遊べるように自分で仲介したり、先生にお願いしたりするようになりました。(過去記事はこちら)
一人遊びばかり続ける子どもが、おともだちと遊ぶのって楽しい!と感じてくれるようになったら、しめたものです。
また、登園前に運動させるため、自宅にトランポリンを買ったのもこの本を読んでからです。(過去記事はこちら)
著者はリン・カーン・ケーゲルという自閉症の息子を持つお母さんです。
彼女の仕事柄、子どもの発達に関心のある学生をベビーシッターによぶ、など、私にはちょっとすぐできない環境でうらやましいなあ、と指をくわえながら読む場面もありましたが、実践につながる事例がたくさん載っていたのがよかったです。
ギフテッド 天才の育て方

キミタロウは、幼少期に自閉スペクトラム症と診断を受けましたが、不器用ながらも普通に運動をし、話すことができる軽度の方だったと思います。
大人になるまでに得意なことを大いに伸ばしてやりたいな。
この本を読んでから、中学受験に挑むか挑まないかを考えたとき、本人のやる気、能力もふまえて、「よっしゃ、親子で一緒にがんばろう~!」と前向きな気持ちになりました。
実際、中学受験に挑んでよかったと思っています。(中学受験に関する記事はこちらから)
ご参考になれば幸いです。







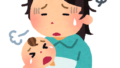

コメント