我が家みたいな共働き一家には特に必要な子育て方針の共有
子育てをおじいちゃんおばあちゃんに頼らず共働き夫婦でする、というのは、骨の折れる仕事です。
なにかと手のかかる子どもがいたりすると、
どうしてもお母さんが主に接するだけでは手が足らず、お父さんにも活躍してもらう場面があると思います。
子どもが発達障がいの診断を受けた、
もしくは病院に相談するほどではないが、なんか手がかかる、
そのような子には合理的配慮で親子共々楽になれることがあります。
しかし、夫婦間でその「合理的配慮」がどれだけ必要か温度感が異なることがあると思います。
その場合夫婦で子どもへの対応の仕方でもめた、という人は結構多いと聞きます。
我が家もそうでした。
わたくしのんびり母さんは我が家の凸凹っぷりのよい子どもらに、
食事中の姿勢親に失礼な言葉遣いをした、呼んでもなかなか返事が返ってこなかった、宿題などの課題に集中できず夜遅くなってわめきながら取り組んでいる、
というようなことで怒りませんでした。
しかし、夫はそのような子どもの行為が気になったようです。
度々子どもに注意をし、私も「なぜ注意しないのか」とずいぶんなじられたことがありました(;^ω^)
私は息子キミタロウの発達障がいの診断をきっかけに勉強をして、
彼らの特性自体を責めても仕方がない、
苦手なことはできるようにサポートしてできた回数が増えていけばいいじゃない、
と思っていて夫にも説明したことはあるのだけどー、
と思いましたが、夫はホントに私がいう対応で大丈夫なのか、と不安になっていた様子でした。
記録は相手を説得するのに有効です
夫婦でどちらかが療育についてよく勉強する場合、
すべてを同じように夫婦で対応するのは現実的ではありませんが、
情報を共有するように努力する必要性をよく感じていました。
勉強している側も専門家ではありませんからね。
説得力のあるものとして役立ったのが、時折私がつけている子どもの記録です。
○月の頃は□□という面が困っていたけれど、親が対応を△△にし始めたら最近は□□はだいぶ回数が少なくなった、
という話ができます。
数字として表せなくても、
表情が明るい、とか、そんなことも話せると思います。
記録をつけておくのはオススメです。

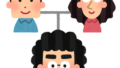

コメント